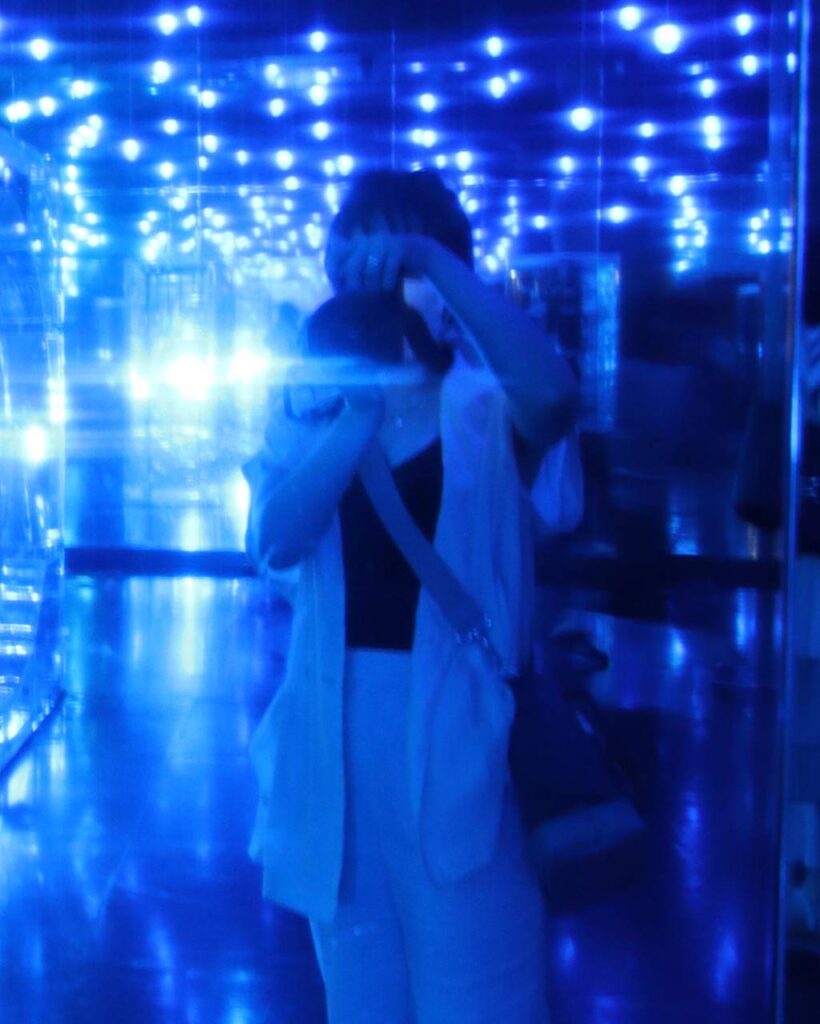ワインについて知りたいけれど、専門用語や香りの表現がむずかしく感じる——。
そんなふうに思っていませんか?
実は、香りの言葉と自分の感覚をつなげるだけで、白ワインの味わいがぐっと立体的に感じられるようになります。
このステップ2では、専門用語と自分の感覚を結びつける方法を紹介します。
たとえば「白桃=みずみずしい甘さの中にあるやわらかな香り」、
「白い花=ジャスミンやアカシアのような上品さ」、
「柑橘系=レモンやグレープフルーツの爽やかさ」。
言葉と香りのイメージがリンクすると、白ワインの世界がぐっと広がります。
ボトルの説明文やレビューも自然と理解できるようになり、
自分の好みの味わいが少しずつ見えてきます。
① “香り”ってどうやって感じるの?
白ワインの香りは、
ぶどうの品種や土壌、発酵の温度、熟成方法などによって生まれます。
同じ品種でも産地が違うだけで香りが大きく変わるのも、ワインの面白いところです。
ワインの香りや味わいの表現には、ほかの食べ物や自然の香りがよく使われます。
果物や花、ナッツなどでたとえられた説明文を、見かけたことはありませんか?
たとえば「白桃の香り」と書かれていても、実際にワインから桃そのものの香りがするわけではありません。
白ワインの場合、白桃のような甘い香りのほかに、酸味やアルコール、発酵由来の香りなどが複雑に重なっています。
そのため、一言で「白桃の香り」と言われても、なかなか具体的にイメージするのは難しいものです。
② 香りを“印象”で理解する3タイプ
香りをもう少し細かく分けると、次のようになります。
それぞれのタイプの特徴を、身近な香りや状況に置き換えてみましょう。
| 香りのタイプ | 感じ方のイメージ |
|---|---|
| フレッシュ系(柑橘・ハーブ) | レモンやグレープフルーツを切ったときの香り。青リンゴやハーブのように、すっきりとした酸味と清涼感がある。 |
| フルーティー系(白桃・洋梨・りんご) | 完熟した白桃や洋梨を思わせる甘い香り。果汁を感じるようなやわらかさとみずみずしさがある。 |
| フローラル系(白い花・ジャスミン・アカシア) | 花瓶に生けた白い花のような、ほのかに甘く上品な香り。香水ほど強くなく、軽くふわっと香る。 |
| ミネラル系(石・海風・雨上がり) | 雨上がりの道や、濡れた石を思わせるようなすっきりとした香り。塩気や金属のようなニュアンスを感じることも。 |
| コクのある系(バター・ナッツ・蜂蜜) | トーストしたパンやナッツ、溶かしバターのような香ばしさ。口に含むとまろやかで、余韻に甘みが残る。 |
香りのタイプは複数混ざることも多く、1本のワインに2〜3種類感じられることもあります。
白桃のような香りを感じるワインには、たしかに白桃のような甘い香りがあります。
ただし、それは単独の香りというよりも、**酸味やミネラル、花の香りなどが重なって生まれる“複合的な香り”**です。
香りはひとつの要素ではなく、いくつもの香りが少しずつ混ざり合ってできています。
だからこそ、ワインの香りは難しく、そしておもしろいのです。
③ 味わいを形づくる要素を知る
白ワインは「辛口」「甘口」、そして「ライト」「ミディアム」などで表現されます。
そこに酸味のキレやアルコールの苦味が加わることで、味わいはより複雑に感じられます。
🔍 甘口でも酸がしっかりしていると、味がぼやけません。
**酸味はワインの“骨格”**とも言われる大切な要素です。
同じ甘口でも、酸味があるかないかで印象はまったく変わります。
酸味を感じながら飲むと、ワインの輪郭がよりくっきり見えてくるはずです。
④ “プロの表現”を自分の言葉に変えてみよう
白ワインは「辛口」「甘口」、そして「ライト」「ミディアム」などで表現されます。
そこに酸味のキレやアルコールの苦味が加わることで、味わいはより複雑になります。
🔍 甘口でも酸がしっかりしていると、味がぼやけません。
**酸味はワインの“骨格”**とも言われる大切な要素です。
同じ甘口でも、酸があるかどうかで印象は大きく変わります。
酸味を意識して飲むと、ワインの輪郭がくっきりと見えてくるはずです。
ワインの世界では「ミネラル感」や「余韻が長い」など、独特の表現がよく使われます。
でも、無理にプロの言葉を覚える必要はありません。
自分の感じ方で言い換えるだけで、ぐっと理解しやすくなります。
| よくある表現 | 感覚で言い換えると… |
|---|---|
| 余韻が長い | 飲み込んだあとも香りがふわっと残る感じ |
| バランスが良い | 甘み・酸味・香りが喧嘩せずにまとまっている |
たとえば私が印象に残っている「クラレンドル・ブラン」も、まさにこの“バランスが良い”タイプ。
白桃のような甘い香りのあとに、柑橘の爽やかさとミネラルの余韻が続きます。
甘やかさと透明感の両方が感じられる味わいで、「白ワインってこういうことか」と腑に落ちた一本でした。
果実味とミネラルのバランスを知るには、ぜひ一度試してほしいワインです。
こんなふうに、自分が感じた香りや味わいを自分の言葉で置き換えることで、
ワインの表現が一気に身近になります。
⑤ まとめ|知識よりも、“感じること”から始めよう
- ワインは知識で選ぶより、印象で味わうとぐっと楽しくなる。
- 香りも酸味も、まずは自分の感覚を信じていい。
- 感じたことを言葉にする練習が、「自分の味覚」を育てる。
“香りを覚える”より、“香りを感じる”ほうがずっと自由。
自分の中に持つ香りの知識を白ワインの香りとコネクトすると
同じ香りで表現される白ワインはイメージできるようになる。
最初は本物のフルーツを買ってきて香りを嗅ぐと、特に香りとイメージが繋がる助けになる。
まとめ
今回は、白ワインの香りと味わいを自分の中で言語化する過程に焦点を当てました。
ワインの表現は難しいものに感じられますが、
実は日常で知っている香り――果物、花、焼きたてのパン、雨上がりの空気――とつなげて考えるだけで、
白ワインの世界はぐっと広がっていきます。
知識よりも、「自分の感覚」を信じて楽しんでみてください。
※ワインの紹介は二十歳以上の方を対象としています。
お酒は二十歳になってから、ゆっくりとお楽しみください。